 |
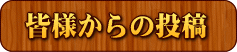 |
 |
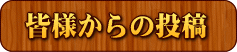 |
| 遊戯の終り PART1 今日も一日が終了し、教室は帰ろうとする生徒、部活に急ぐ生徒のにぎやかな声に満ちていた。ここ聖仙学園高校1年1組の教室で、櫻井勝弘はフウッと意味もなく溜め息をついた。6月の今、各クラブの勧誘も終わったが勝弘はどこにも属していなかった。県内の偏差値最上位校である聖仙に入学したはよかったがそこが限界、授業についていくのに精一杯の勝弘には、どこかのクラブに入る余裕など全くなかった。かといって直ぐに帰る気にもならないし帰っても家には共稼ぎの両親をはじめ、誰も帰っていない。寂しさがつのるだけの放課後は時間つぶしに困り、孤独感だけを募らせる一番嫌いな時間だった。どうしようかなあ・・・でも帰って復習しないと・・・返されたばかりの中間テストの成績を思い出した。最下位から5位、酷い成績だった。あれだけやったのにな・・・奇跡的に合格したはいいものの、自分の学力が学年最下位クラスなのを思い知らされる成績だった。誰もいない家で、一人机の前で勉強か・・・小柄で細身、性格も陰気な勝弘は、未だ友達らしい友達もいない。どこかクラブにでも入ろうかな、何度となく考え、その都度諦めた考えに頭を振る。無理だよな、運動なんか全部ダメだし、かといって音楽も美術も全然好きじゃないし・・・好きなのは・・・漫画?それも読むだけだもんな。描くのなんか全然できないし。ハアッ、外の景色に目をやった。梅雨の晴れ間、珍しい程の青空が不快だ。こんな日に限って天気も良くて日が暮れるのだけは遅いし、部活やってる連中は気持よさそうだし・・・つまらない・・・溜め息をつきながら荷物をまとめ、帰ろうとした勝弘を、凛とした声が咎めた。 「ちょっと櫻井君、今日掃除当番でしょう!?ズルして帰っちゃダメ!ちゃんと手伝ってよ!」 ビクッと震えた勝弘が振り向くと、一人のクラスメートが睨み据えていた。ショートカットの髪を前髪だけ長く伸ばし流している。小さな顔に大きな瞳が映える。どんぐり眼ではない、むしろ切れ長といった感のあるやや吊り目の、黒目がちな瞳は強烈な意志力と他人を射竦めるようなカリスマに満ち溢れ、同時に吸いこまれそうな透明感も兼ね備えている。じっと見詰められると、圧力を感じる程の目力を放つその瞳は、一たび怒気をはらめば男女を問わず、まともに目を合わせることなど到底できない、魔眼と呼ぶのが相応しい程の迫力となる。さほど背は高くないが、引き締まった体はいかにもアスリートらしく、運動神経に満ち溢れ俊敏そうだ。声の主は住吉真希、バスケ部の新鋭でクラス委員、成績も学年トップとの噂の美少女。上品で育ちがよく、実家も裕福なお嬢、甘やかされた我儘ではないが極めて真面目で正義感が強く、曲がったこと、筋の通らないことが大嫌いな優等生。余りにストレートな、誰はばかることない王道の美少女は、勝弘のように歪んだ卑屈な小男には一番苦手な相手だった。別に苛められた訳ではない。相手にもされていない。だが何もない勝弘にとって、成績も運動神経も男女を問わずの人気も、全てを持っている真希は羨ましいを通り越して眩し過ぎ、疎ましい存在だった。
一瞬驚いた真希は景子を見詰めた。まさか私がリンチするだなんて、考えてもみなかったけど・・・動揺しながら真希は、勝弘を睨み据えた。でも、景子の言う通りかもしれない。勝弘が自分のことを苦手とし、怖がっているのは真希もよく分かっていた。掃除を命じたのも私、勝弘が唯花のマウスピースを穢すチャンスを作っちゃったのも私・・・じっと勝弘を睨み据える。おどおどと恐怖に満ちた目で自分を盗み見る様が、何とも穢らわしい。卑屈に怯えながら、惰弱な希望を微かに浮かべた視線が吐き気を催すほどおぞましい。勝弘ったら、私がいざ自分がリンチするとなったら、怖気づいてやっぱりやめよう、何て言いだすのを期待しているのね。この・・・クズは!新たな怒りと共に、真希は決意を固めた。よおし。大きく息を吸った。
「いいわ、言いだしっぺだしね、私がリンチするわ。」 チラッと時計を見た。昼休みはもう余りない。 「今はもう時間がないから、今日の放課後、クラスルームが終わり次第、勝弘をリンチするわ。逃げたり逆らったりできないように、みんなも手伝ってね。」 くうううっっっ、教室に微かな呻き声が響いた。勝弘の嗚咽だった。真希に、よりによってクラスで一番苦手な真希に、一睨みされただけでコンプレックスの塊にさせてしまう真希にリンチされる。その恐怖と絶望に耐え切れずに、早くも嗚咽を漏らしていた。 チャイムが鳴り、5時間目が始まった。真希は硬い表情のまま、殆ど一言も発せずに授業を受けていた。そして休憩時間に、唯花が尋ねた。 「真希・・・勝弘のことリンチするって、どうやるの・・・無理、しないでね。ううん、勝弘のことなんか、これっぽっちも心配してないよ。真希のことが心配なの。だってぶったり蹴ったりして怪我させちゃったりしたら、真希がまずいことになっちゃうんじゃないの?」 「大丈夫。心配しないで。」 ゆっくりと真希が答えた。 「私もね、さっきは思いっ切り殴ってやろう、剣道部から竹刀とか木刀とか借りてきて、思いっ切り殴ってやろうか、て思っていたわ。だけどね、景子の言ったことをよく考えてみたの。ぶったり蹴ったりしても、勝弘みたいなクズは逆恨みするだけだ、と言ったことをね。そうだと思う。ぶったり蹴ったりするだけだなんて、生温すぎるわ。だから私ね、勝弘の精神をグチャグチャに踏み躙ってやるわ。一生忘れられない位の辱めを与えて、消しようがない位のトラウマを刻み込んでやるわ。」 冷笑、唯花が寒気を感じる程の凄絶な冷笑を浮かべた。 「勝弘の体には、傷一つつけないと思うわ。だけど・・・気が狂いたくなるほど辱めて、再起不能にしてやるわよ。」 真希の邪眼に射竦められ、勝弘は心の底から震え上がっていた。リンチ・・・リンチ・・・何をされるんだろう・・・引っ叩かれる?蹴りのめされる?真希と唯花の話など聞こえもせず、勝弘はひたすら肉体的な苦痛だけを恐れていた。自分を憎々しげに睨み据えた、真希の美しくも恐ろしい形相が頭にこびりついて離れない。女の子にリンチされる・・・非現実的な真希の宣告、だが真希なら、あの形相の真希なら・・・本当に僕をリンチするに違いない・・・女の子に殴られ蹴られる・・・悪い夢としか思えないほど強烈に屈辱的だ。だけど・・・微かな救いを必死で見出そうとした。・・・大丈夫、どんなに怒ってたって、真希は女の子なんだから・・・そんな酷いことにはならないよ・・・大して痛くはないさ・・・でもまさか・・・なんか道具とか使わないよね・・・竹刀とか、木刀とか・・・ 勝弘はリンチと聞いて、単純な暴力だけしか想像できなかった。少しでも痛くなく済めばいいな、それ以外のことは、一切考えていなかった。真希が竹刀とか木刀とか、そんな単純なリンチなんか考えてもいないことなど、想像することすらできなかった。何をされるか分からない恐怖が、勝弘の惰弱な精神をゆっくりととろ火で炙る。5時間目、休憩時間、そして6時間目・・・教室の壁に掛けられた時計が、轟音にも似た音を立てて時を刻んでいるようだ。胃の中がせり上がってくるような恐怖。ゆっくりと時を刻む、時計の緩慢な動きが呪わしい。嫌、リンチなんかされたくない・・・このまま時間など止まって、との願いを嘲笑うかのように、止まることなく動き続ける秒針が忌わしい。
|
| 黒ギャルM男イジメ
|
||
|