 |
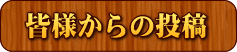 |
 |
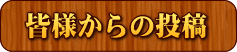 |
| 遊戯の終り PART2-1 誰もいなくなった教室、つい今したがたまで生き恥を晒されていた教室で、勝弘は肩を震わせ泣き咽びながら思い悩み、堂々巡りを繰り返していた。ひ、酷いよ真希、あんなに、あんなに苛めるなんて・・・幾らなんでも・・・ち、くしょう・・・唾を吐き掛け勝ち誇り顔を踏み躙った美貌が脳裏に焼き付いている。
その鋭い視線に火のような言葉に、射竦められ屈従した自分の姿がどうやっても消せない。教室のど真ん中で、クラス中のみんなが見ている前で唾を吐き掛けられくつをなめさせられ、公開で辱められたのだ。全身を恥辱の火、じくじくと燻ぶり何時までも消えない火にゆっくりと炙り焼きにされている。 う、ううう・・・ヒック・・・鼻を啜った瞬間、ツンとした金属質の微かな臭いが鼻を襲った。 つ、唾の・・・臭い、真希の唾の臭い・・・顔中に履き掛けられ靴底で擦り込まれた唾が、ゆっくりと乾きつつあった。蒸発したのか、顔に浸み込んだのかも分からない。顔一面に、乾いた唾で薄い膜を張られたようだ。パリパリと強張ったような感じがする。息をするたびに、真希の唾の臭いがする。顔を洗っちゃ駄目。今日一日、私の唾の臭いと一緒に過ごしなさい。女の子の唾の臭い。生々しい心の傷に新たな塩を絶え間なく擦り込む唾の臭い。そして真希の残酷な命令を、忠実に実行している情けない自分。だが勝弘を責め苛んでいるのは、唾の臭いだけではない。どうやって掃除したらいいか、分っているわね。 真希の最後の言葉が耳にこびりついて離れない。 ち、くしょう・・・教室中に散らばった唾を掃除しておけ、だなんて・・・自分が吐き掛けたくせに・・・自分の顔めがけて吐き掛けられた唾を、自分を辱め責め苛んだ女の子の唾を掃除する、屈辱の極みだ。だが逆らえない。 いやだいやだと文句を言いながらも、自分が掃除してしまうことだけは、誰よりも勝弘自身が一番よく分かっている。やればいいんでしょ、やれば。だけど・・・掃除の仕方が問題だった。教室の片隅にある、掃除用具を見る。モップもある。モップで拭けば簡単なこと、直ぐ済む。だけど・・・どうやって掃除したらいいか、分っているわね。真希の意に適っているだろうか。頭を掻き毟る、何本もの毛が抜け落ちる。 なんで、真希のご機嫌を取らなくちゃいけないの!?だけど・・・だけど・・・目の前の床を見る。最後に吐き掛けられた唾が顔から滴り落ち、溜まっている。未だ泡が残っている唾の塊まである。顔から滴った唾の糸のいくつかは合体し、小さな池、唾の池のようになっている。 美しい真希、気高い真希、優等生の真希。クラス全員の真希像は、勝弘にだけは違う。意地悪な真希、冷酷な真希、残酷な真希。そして勝弘が思い描く真希の命令は疑う余地もなく、こうだった。跪いて私の唾を、一滴残らず舐め清めなさい。 や、やだ!そんな、こと・・・ふ、拭いちゃおう、今すぐモップ持ってきて拭いちゃおう。み、見てない誰も、見てないんだから今のうちに・・・だが体が動かない。立とう動こう、幾らそう頭で考えても虚しく言葉が空回りするだけ、勝弘の手も足もプルプルと力なく震えるだけだ。 駄目・・・出来・・・無い…ついに勝弘はがっくりと力なく頭を落とした。真希には・・・逆らえ・・・ない・・・逆らう?真希は何も言っていない。 掃除しなさい、どうやって掃除したらいいか、分っているわね。そう言っただけだ。だけど・・・真希が思ってるのと違うことしたら・・・また苛められる・・・唾、吐き掛けられる・・・唾を、みんなの見ている前で唾を吐き掛けられる。それだけは、それだけはもう絶対に嫌だった。そ、それ位なら、あんな目に遭わされる位なら・・・未だこの方が・・・誰にも気にもされず見られもしない中、一人勝手に真希に屈服した勝弘の貧弱な細い両手から、力が抜けて行く。顔が床へと近づいていく。 床にできた小さな池、真希の唾池へと顔を近づけて行く。もうほんの目と鼻の先に唾池がある。 ワナワナと震えながら舌を突き出し、唾池へと伸ばす。 あ、あああ、あああああ・・・ピチョッ、遂に舌の先が真希の唾に触れた。床に滴り冷めきった唾、冷たい液体の感触。思わず舌を引っ込めてしまう。まじまじと唾池を見る。床に広がる小さな池は、全く減っていない。汚辱を吐き気を堪えながら、意を決して2回、3回と舐める。ピチャペチャ、床に舌が触れる。固いヒンヤリした感触。床を舐める、真希も唯花もそして自分も、クラスみんなが歩き回っている床を舐めている。 それだけでも十二分に屈辱だが、今はそれすら問題ではない。 どう?顔を持ち上げ見下ろす。あああ、駄目、全然減ってない・・・舐め清めたつもりが、唾池を周りに広げただけで全然減っていない。却って床を汚してしまったようなものだ。うぐうううっく、しょう・・・こうするしか、ないのかよ・・・呪いの言葉を吐きながら、勝弘は真希の唾に口を近づける。真希が吐き掛けた唾、自分の顔を汚し、床に垂れた唾に口付けする。ズッ、ジュルウッ・・・息を吸い込み真希の唾を吸い上げる。少しずつ、少しずつ真希の唾が口の中に吸い取られる。ウグウッ、エグウウウッッッ・・・吐き気が込み上げる。 女の子の唾を吸い取っている。自分の顔に唾を吐き掛け辱めた女の子の唾を吸い取っている。悪い夢のような現実。誰もいない教室で、自分の意思で、惰弱さで繰り広げている痴態。涙が出る程惨めな行為に、涙が溢れ出るのを抑えられない。 ヒッヒック・・・フエエエエエッ・・・泣きながら真希の唾を吸い取り続ける。あらかた吸い取ったところで、再度床を舐め清める。レロエロレロ・・夢遊病患者のように、呆けた顔で舌を動かし続ける。床に残る真希の唾の残骸を舐め清める。 こ、ここは・・・きれいになった・・・次は・・・床に這いつくばったまま、次の唾を探す。すぐ50センチ先に、1メートル先に、あちこちに真希の唾が待ち受けている。あれを・・・全部、舐め清めるの・・・気が遠くなるほどの絶望。現実感を失うほどの屈辱悪夢に必死で耐えながら、真希の唾を舐め清め続ける。みんなが自分が歩いている床を舐めているだけでも、気が狂うそうな程の屈辱だ。 ましてや自分を屈辱地獄に突き落とし晒し者にした、憎い憎い真希の唾を舐めているのだ。考えたくない考えない、絶対何も考えたくない、考えたら耐えられない・・・必死で頭を振りながら、惨めな床掃除を続けた。チュバッ、チュウッチュチユッ・・・ピチャペチャレロ・・・誰もいない教室に、卑しい音が響き続ける。 嫌というほど唾を吐き掛けられた教壇を、30分以上かかって漸く舐め清め終えた。 次は・・・机と机の間を見て絶望に項垂れてしまう。通路のあちこちに、真希の唾が飛び散っている。真希に唾を吐き掛けられながら教室中を追い回された、辛い辛い心の生傷が塩を擦り込まれたかのようにジクジク傷む。 これを・・・全部、舐めるのか・・・目の前が真っ暗になりそうだ。必死で頭を振り床を見つめる。かかか、考えるな考えるな・・・舐める、兎に角・・・きれいに・・・するんだ・・・それだけ、それだけを・・・かんがえ・・・よう・・・全力を振り絞り頭の中を空っぽにし、一番手近な唾に舌を伸ばし舐め取る。ペチャピチャ、少し先にも唾が見える。首を伸ばして舐め取る。 直ぐ先にも別の唾が・・・通路のあちこちに真希の唾が散らばっている。一つ一つの唾は池になる程の大きさではないが、追い立てられながら吐き掛けられたため、そこかしこに細かい唾が散らばっている。勝弘はいつしか、体を起こすことすらしなくなっていた。一々立ち上がるのも面倒、等と考える気力すらない。四つん這いのまま真希の唾から唾へと這いずり回り、床を舐め続けていた。 惨め、惨め、惨め。誰もいないのが唯一の救いだ。 舌と手足だけを動かす、何の感情もない機械のように感情を押し殺しながら、真希の唾の残骸を舐め続けた。廊下に響く靴音も、教室のドアが開かれたことにも気付かずに。
いかに屈辱の唾とはいえ、人畜無害の液体、それもほんの数滴ずつの液体を吐き掛けられているだけなのに、硫酸にも勝る強力な溶解液を吐き掛けられているかのように、顔中が熱く燃えるように痛い。痛いだけではない、真希の唾に顔も精神も何もかも、微かに残っていたプライドらしきものも全て、ドロドロに溶かされてしまっているかのようだ。
イダイ・・・アジュイ・・・比喩でも何でもなく、勝弘は真希の唾により、耐えることなどできない程の苦痛に責め苛まれていた。真希の唾は一撃ごとに、勝弘の惰弱な精神に残された僅かな心的防御を、確実に打ち砕き溶かし崩し、確実に責め落としていった。 何度唾を吐き掛けられただろうか、勝弘の口がワナワナと震えている。首がガクガクと今にも落ちそうに震えている。残酷な真希の唾に、勝弘の全ての心的防御は完膚なきまでに打ち砕かれてしまっていた。もう限界だった。 欠片ほどのプライドもちっぽけな怒りも、全てが真希の唾に蹂躙し尽くされていた。や、やべでよ・・・もう・・・ダメ・・・ねがい、お願いだよおおお、唾は、もう・・唾は・・・ゆるじで・・・怒りなどもうとっくに真希の唾に打ち砕かれてしまっていた。 もう、唾を吐き掛け責め立てる真希に、哀願し赦しを乞う、哀れな虫けらに堕とされていた。最後の心的防御すら打ち破られてしまっていた。顔だけは未だ上を向いている。だが首の筋肉は真希の唾に、既に全ての力を焼き尽くされもう何の力も入っていない。 単なる惰性で上を向いているだけに過ぎない。そして今、最期の止めの唾が、一際大きな唾の塊が鼻頭に、叩きつけられた。あ、あああ・・・ううううう・・・勝弘は、精根尽き果て全ての抵抗力を失い、唾塗れの汚い顔をガックリと項垂れた。 せめてもの意地、顔をあげ真希を仰ぎ見ることさえ、もう出来なかった。 床についた手からすら力が抜けてしまい、正座したまま顔を床に埋めるかのように崩れ落ちた。顔中から、真希の唾が滴り落ちている。一発のビンタも一発の蹴りも受けた訳ではない。 唾で、唾だけで、これ程までに、呻き声すら上げられない程に打ちのめされ、屈服させられてしまったのだ。アウ、ウウウ・・・啜り泣きながら勝弘は半ば無意識に呟いた。 ご、めんなさい・・・ごめん、なさい・・・自分の口から洩れた言葉に耳を疑う。自分の姿勢に気付く。両手を折り曲げ床にひれ伏し額を点けている。土下座。真希の足元に土下座しているかのようだった。 ぼ、ぼく・・・土下座・・・真希の、真希の足元に・・・土下座、している・・・土下座だけではない。真希に、真希に・・・謝っている・・・唾を吐き掛け自分を苛めている真希に・・・謝れ、なんて言われてもいないのに・・・自分の姿勢自分の声、自分が何をしているのか、誰に言われずとも、自分自身が一番良く分かっていた。 真希の足元に土下座し赦しを乞うている。そう、自分は負けてしまったのだ。真希に屈服してしまったのだ、ということを。 凄まじい屈辱だった。これほどまでの敗北を味わったことは、あらゆることを通じて生まれてこの方、間違いなく一度もなかった。ま、負けた・・・真希に・・・負けた・・・涙が零れてくる、溢れてくるのを止めようがない。 お、女の子に・・・泣かされた・・・つ、唾で・・・唾で、唾だけで、屈服、させられてしまった・・・修羅の形相で唾を吐き掛ける真希の美貌が、間断なく唾を吐き掛けるふっくらとした真希の美唇が、脳裏を支配する。 自分は・・・真希に完全に屈服してしまった・・・真希に泣かされて・・・こうやって土下座している・・・絶望的な迄の敗北感だった。もう・・・真希には絶対逆らえない・・・悔しさすら、もう出てこない。完璧な敗北は心地良い、など全くの嘘だった。 あるのは唯々、惨めさと絶望だけだった。もう一生、真希には・・・逆らえない・・・顔を見ることさえ・・・怖い・・・そして新たな恐怖を認識してしまった。真希がこのまま自分を放っておいてくれる筈がないことを。そしてこれから先、どんな目にあわされようとも、自分が絶対に逆らうことなどできないことを。 怖い・・・な、何を・・・されるの・・・どういう・・・目に、遭わされるの・・・その恐怖は、紛れもない現実、真希がこれから味合わせようとしている現実だった。 うう、あうううう・・・うう、えええんんん・・・屈辱と絶望と恐怖に肩を震わせ、ボロボロ涙を零して泣き出す勝弘を、真希は冷たく見下ろしていた。ハア、ハアア、ハアアアアッ!怒りの余り、吐く息すら荒い。 自分の足元に土下座している勝弘を、唾で打ちのめし人格崩壊させてやった惨めなクラスメートを見ても、哀れとも何とも思わなかった。 達成感はある。大嫌いな勝弘を屈服させてやった、ウジ虫を泣かせてやった達成感はある。いい気味! だが快感など全く感じていない。憎悪の獄炎はより一層激しく燃え上がっていた。だいっきらい、勝弘、あんたなんか・・・大嫌い!私を、こんなに嫌な気分にしてこんなに怒らせて、一体どういうつもりなのよ! 赦さない、絶対に赦さないから!リンチしてやる、苛めてやる・・・一生忘れられない位、酷い目に遭わせてやる。 唯花に変態した罰じゃない、私に、この私にこんなに嫌な思いをさせた報いを与えてやる。覚悟しなさいよ。キッと美唇を噛み締め、宣告した。私に?二度三度、深呼吸する。そうよ、ここから先は私のために、私に嫌な思いさせた報いに・・・リンチしてやる。 制裁のためでもなく誰のためでもなく、純粋に自分自身のためにリンチする。今の今まで想像したこことすら無かった自分の決意。だがその決意は真希にとって、何より自然に受け入れられる決意だった。 何の躊躇もなく何の興奮もなく、水を飲むように空気を吸うように、極く当然のこととして宣告した。「勝弘・・・絶対に赦さないからね、思い知らせてやる・・・リンチ、再開よ。」 スッと右足を上げ、何の躊躇もなく土下座する勝弘の頭に下ろす。全体重を右足に掛ける。 ううっぐううう・・・呻き声を気にもかけずに、踏み付けた右足を左右に間断なく動かし、踏み躙る。 靴で、土足で他人の頭を、顔を踏み躙っている。今朝起きた時には、そんなことを自分がするなど、想像することすらなかった。だが今はごく当然のこととして踏み躙っている。 何の抵抗も感じない。何の憐れみも感じない。極く当然のこととして、勝弘の頭を踏み躙っている。 土下座して自分に赦しを乞うている勝弘、その哀願を拒絶し頭を床にめり込ませんばかりに、激しく踏み躙っている。 嗜虐心は純粋さを増していく。考えているのは、どうやって苛めてやろうか、どうやって辱めてやろうか、ということだけだ。キッと美唇を噛み締め腕組みして下を見下ろす。白い上履きとその下で蠢く黒い頭を見下ろす。 ジョリッジョリッと靴底に踏み躙られた髪の毛が擦れる音がする。この頭の下、どうなっているのかしら。きっと鼻も口も床にめり込んで、さぞ痛いでしょうね。だがやめる気など毛頭ない、更に体重を掛けて踏み躙る。 ウッアックウウッッッ、痛みと圧迫に耐えかねた勝弘は、顔を横に向けてしまう。 何よ横向いちゃって、痛そうにすれば赦して貰えるとでも思っているの? 足を上げもせずに右足を移動させ、今度は頬を踏み躙り続ける。 自分が吐き掛けた唾を、しっかり擦り込んでやるかのように。勝弘の頬に、自分がつい今しがた吐き掛けた唾が光っている。その唾ごと勝弘の頬を踏み潰しながら、激しい苛立ちに駆られる。 唾がついちゃったじゃない!幾ら私の唾だ、て言ったって、何で私の靴を唾で汚さなくちゃいけないのよ! 傍らの椅子に腰かけようとしたが、ふと手を止めた。さっきと同じようにして舐めさせるなんて、芸がないわね。椅子を教壇の端に上げてから腰を下ろし、悠然と美脚を組む。30センチ程の教壇の上から、床に土下座する勝弘を見下ろす。 唾を吐き掛けた自分の足元に蹲る男。惨めね。フッと美唇が微かに冷笑する。 「勝弘、顔上げなさいよ。」 腕を組み、傲然と命じる。 「勝弘の汚い顔踏んだから、汚れちゃったじゃない。きれいに舐めて掃除してよ、私の靴底を。」 床からのそのそと体を起こした勝弘が、恨めしそうな目で見上げている。 文句あるの?等と聞く気もしない。 「だらしない格好ね、私の靴を舐めるのよ、失礼じゃない、ちゃんと姿勢正しなさいよ!」凛とした声で命じる。目だけは恨めしそうにしながらも、勝弘は言われるがままに正座し、両手で突き出された真希の右足を押し頂いた。 ペロピチャペチャ・・・靴を舐め清める音が微かに響く。責める真希は、自分の靴の更に下にウジ虫の顔を見下ろしている。 責められる勝弘は、突き出された足の遥か上に、女神の美貌を見上げている。強く凛とした視線と弱く怯えた視線が交錯する。何て惨めなの・・・自分の靴を舐めさせながら、真希は嫌悪感で胸がむかむかしてきた。こんな奴、もっともっと酷い目に遭わせてやらなくちゃ、赦せない。こうやって延々と私の靴底舐め続けるだけだなんて・・・こんなんじゃ、さっきやらせたのと同じじゃない。ううん、みんなが見ていない分、勝弘にとっては未だ堪え易いかもしれないわ。 ダメ、これじゃ足りない、こんなんじゃ手緩すぎよ・・・
|
| 集団ツバ吐き
|
|
|