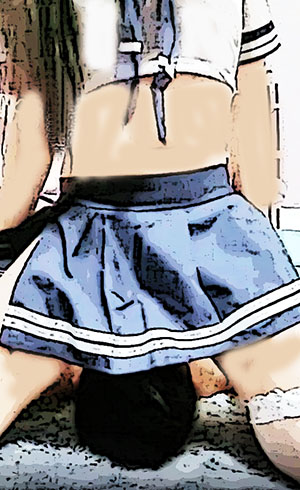因 縁 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者 namelessさん |
||||||||||
| 四月初めのうららかな春の日差しの中、竹中慎吾は赴任先である公立高校の校舎を、感慨深げに見上げた。その高校は、彼の出身校だった。 (卒業して、もう25年になるのか…) しかし、今年43歳になる慎吾には、母校とはいえ、高校時代を懐かしむ気持ちは全く無かった。彼はこの高校で酷い虐めを受け、心に深い傷を負い、高校教師になっても、母校への赴任は出来るだけ回避してきたのだ。 慎吾は小さくため息をつくと、軽く頭を振り、校舎に入って校長室に向かった。彼は校長室で赴任の辞令を受け取り、職員室で同僚教師達に挨拶を済ませて、受け持ちクラスの引き継ぎを受けた。与えられた机で、資料や書籍の整理をしながら、慎吾は自分の悲惨な高校時代を回想した。 中学時代の慎吾は、勉強が出来て成績が良く、有名私立高校を志望していた。しかし、受験期間に重度のインフルエンザに罹ってしまい、10日間位寝込んで、志望校への受験が出来なかった。インフルエンザが抜けて、ようやく起き上がれるようになった時、殆どの高校受験は終わっており、定員割れでまだ生徒を募集している公立の底辺高校しか残っていなかった。 慎吾はやむを得ず、男女共学であるその公立高校に入学した。勉強は出来るのだが、身長160㎝位で、痩せていて小柄な慎吾は、スポーツが大の苦手で内気な性格のため、周囲の同級生とは反りが合わず、友達らしい友達は殆ど出来なかった。 彼はヤンキーの生徒に目を付けられないように、息を殺して大人しく高校生活を送っていた。二年生までは、何とか平穏無事に過ごせたのだが、三年生になった時に問題が起きた。 放課後に慎吾が帰宅するのに近道しようと、体育館裏にある小さな路地に向かうと、女生徒数人の話し声が聞こえた。体育館裏では、同じクラスの坂上今日子が、彼女の取り巻きと煙草をふかしながら、お喋りしていた。今日子は女子バレーボール部のキャプテンで、身長175㎝はある大柄な体格で力が強く、男子とも平気で喧嘩するくらいに気性が激しいので、ヤンキーの男子生徒も彼女には一目置いて、敬遠していた。 喫煙していた今日子と目が合った慎吾は、気が動転し、急いで引き返した。心臓をドキドキさせながら、早足に戻る途中、クラスの担任教師とすれ違った。 「竹中、どうしたんだ?えらく顔色が悪いぞ」 「い、いえ、何でもありません」 担任教師に尋ねられた慎吾は、慌てて誤魔化して、そのまま帰途についた。 翌日登校して教室に入ると、今日子が凄い目つきで慎吾を睨んだ。慎吾は、小柄な体を竦ませて怯えたが、 (坂上さん達が煙草を吸っていたのを見かけただけで、何もしてないから大丈夫だよな…) と自分に言い聞かせた。 授業中は特に何も無かったのだが、授業が終わって放課後になり、担任教師が姿を消すと、慎吾は今日子と、彼女と同じ女子バレー部員である取り巻きに囲まれた。今日子の口から、ドスの効いた声が発せられた。 「…竹中君、話があるの。ちょっと顔貸してもらえる?」 気弱な慎吾は竦んでしまい、大柄な今日子の顔を見上げながら、震え声で何とか答えた。 「えっ、いや、あの…今日は急いで帰らないと…家に用事が…」 「とぼけるんじゃないよ!一緒に来な!」 今日子に一喝された慎吾は縮み上がり、彼女の取り巻きに囲まれたまま、女子バレー部の部室まで連れて行かれた。 部室に慎吾を入れた今日子は、ドアに鍵を掛けると、いきなり慎吾の頬を思い切り平手打ちした。 「ひいぃっ」 全国大会出場常連校の女子バレー部キャプテンで、エースアタッカーでもある大柄で力の強い今日子から、力一杯平手打ちされたのだから、堪ったものではない。小柄で非力な慎吾は、哀れな悲鳴を上げ、首を横にしてふっ飛び、部室の床に横倒しとなった。 今日子の取り巻きで同じ女子バレー部員の、体格のいい大柄な女生徒達が、倒れた慎吾をドカドカと蹴りつけながら、罵声を浴びせた。 「何偉そうに寝てるんだい!さっさと起きなよ!」 「センコーにチクる卑怯者が!」 「起きて正座するんだよ、正座!」 体中の骨を蹴り折られるような恐怖を覚えた慎吾は、 「ひいっ、ひいっ、直ぐ起きます、正座しますから…」 と泣き声で答え、何とかその場に正座した。 今日子は、すすり泣いて正座している慎吾の髪を掴み、引き上げて、自分の怒った顔を近づけた。今日子の怒気に満ちた表情は、なまじ綺麗な顔立ちをしているので、壮絶な凄みがあり、慎吾を心底震え上がらせた。 「お前…あたしらのタバコを先公にチクったね!」 今日子のドスの効いた問い掛けに、慎吾は慌てて泣き声で否定した。 「い、いいえ、僕は誰にも話していません…」 途端に、目から火花が散るような強烈な往復ビンタが、慎吾の両頬に張られた。 「ひいっ、ひいいっ」 哀れな悲鳴を洩らす慎吾を、今日子は怒鳴りつけた。 「とぼけるんじゃないよ!お前がどっかに行った後、何か嫌な予感がして、みんなが吸ってた煙草を踏ませて靴裏に隠した途端、担任が来たんだ。間一髪で見つからなかったけど、お前がチクったとしか考えられないんだよ!」 慎吾は戦慄したが、それでもべそをかきながら、何とか抗弁した。 「いえ、違います…先生が来たのは、ただの偶然です…僕は本当に話していません。信じて下さい…」 しかし今日子の返事は、慎吾のみぞおちに入った鋭い蹴りだった。 「ぐええっ」 体を二つ折りにし、腹を押さえて床にのたうち回って苦しむ慎吾を横目に、今日子は取り巻きの女子部員達に声を掛けた。 「みんな、こいつは言い訳ばっかりして、全然反省してないね。裸にひん剥いて、ヤキを入れてやろうよ!」 賛同の声を上げた女子部員達は、今日子と一緒になって、慎吾に飛び掛かった。慎吾はみぞおちの痛みに耐えながら、必死に抵抗した。しかし、スポーツと縁の無い小柄で非力な慎吾と、大柄で体格のよい、バレーで鍛えた女生徒数名とでは、勝敗は言うまでもなかった。 慎吾は、制服は勿論、下着も靴下も全て剥ぎ取られ、生まれたままの姿にされた。彼は、男の自分が女に力ずくで服を剥ぎ取られて、全裸にされた恥辱で顔を紅潮させ、床にうずくまってすすり泣きの声を漏らした。 しかし、今日子達は慎吾をこのまま悲しみに浸らせてやる程、優しくはなかった。何しろ、リンチはこれからなのだ。今日子はうずくまっている慎吾の頭を蹴って、命令した。 「男のくせに、メソメソ泣くんじゃないよ!泣いてる暇があったら、とっととお立ち!立たないのなら、みんなで蹴り殺すよ!」 慎吾は、先程女性部員達によってたかって蹴られた痛みと恐怖を思い出し、ヒックヒックと嗚咽を漏らしながらも、何とかよろよろと立ち上がった。今日子は慎吾が立ち上がったのを見て、更に酷い命令を下した。 「両手は頭にやって、足は肩幅に開くんだよ!」 今日子に怯えきっている慎吾は、恥ずかしさと口惜しさに耐えて、言われた通りのポーズを取った。その時、ピカッとフラッシュが光り、シャッター音がした。女子部員の一人が、使い捨てカメラで慎吾の裸体を撮影したのだ。慎吾は、他の女子部員がビデオカメラを回しているのにも、気がついた。今日子達は慎吾を嬲るため、周到に準備していたようだった。 今日子の声が響いた。 「さあ、腰を突き出して、こう言うんだよ…『僕の貧相で醜いものを、見て下さい』ってね!」 慎吾は屈辱で身震いしたが、とても今日子に逆らう勇気は持てずに、両手を頭にしたまま、腰を突き出した。 「ぼ、僕の…貧相で…醜いものを…見て…下さい」 慎吾は嗚咽混じりの声で、途切れ途切れに今日子の言った事を、どうにか復唱した。途端に、慎吾の股間のものを指差していた女子部員達が、どっと爆笑した。 「キャハハッ、何よあれ!あんな皮を被った小さいものをブラブラさせて、恥ずかしくないの?」 「おっかしーい!女の前で、よくそんな格好が出来るわね」 「アハハッ、ちっさーっ!あたしの彼氏のと比べたら、赤ちゃんみたい!」 女子部員達の嘲りが慎吾の胸を抉り、恥辱で顔から火が噴き出る思いを味わされた。その間にも、カメラのフラッシュが光り、ビデオカメラは回されている。 「フフン、次は裸踊りをして、あたしらを楽しませな!」 今日子に命じられたものの、慎吾にダンスの経験があろう筈もなく、どうやって踊ればいいか解らずに、とまどっていた。すると、今日子は脱がせた慎吾のズボンから革ベルトを引き抜き、それで彼の腰回りを力強く叩いた。 「ギャアァーッ」 慎吾は悲鳴を上げ、体を二つ折りにして苦しんだ。彼の腰辺りに、一条の赤い筋が見る見る浮かび上がった。 「踊れと言ってるのが、聞こえないの?それとも、聞かないつもりかい?」 「ひいっ、そんな事ありません…」 慎吾は泣き声で答え、慌てて手足を動かした。しかし、彼の動きはとても踊りとは言えず、故障したロボットが潤滑油の切れた状態で、でたらめにぎこちなく動いているようで、見物している女子部員達の失笑を買った。 「もっと滑らかに踊るんだよ!」
慎吾は額を床に強く押しつけられながら、苦痛と屈辱に震えた声で返事をした。今日子が足を外し、慎吾の頭が急に軽くなった。 「さっさと中腰になって、オナニーしな!」 今日子に怒鳴られた慎吾は、中腰になって股間のものをしごき始めた。フラッシュが光り、ビデオカメラが向けられ、女子部員達の熱い視線が自分の股間に集中しているのを、痛い程感じていた。しかし彼のものは、今日子への畏怖と度を超えた恥辱で萎縮してしまい、全く勃起しようとしなかった。今日子からの制裁を恐れた慎吾は焦ったが、こればかりはどうにもならなかった。 「全くもう、まどろっこしいわね…仕方ないから、元気づけてあげるわよ」 今日子は制服のスカートを捲って両手を差し入れ、何の恥ずかしげもなく慎吾の目の前でパンティを脱ぎ、パンティの汚れたクロッチ部分を彼に見せつけた。そのクロッチ部分には黄色く濃い染みが広がり、後ろ側には茶色い筋も付着していた。 「ウフフ、生理前でおりものが多いから、汚れてるのよ」 今日子は、汚れた部分が慎吾の鼻と口に当たるように調節して、パンティをマスクのように慎吾の顔に被せた。 「ムウゥッ」 饐えたような女の強烈な臭いが慎吾の鼻孔に侵入し、彼は思わず呻き声を漏らした。しかし、その強い女臭が、若い慎吾の肉体に変化をもたらせた。あれ程萎縮していた股間のものが、不覚にもムクムクと頭をもたげて、硬く屹立してしまったのだ。見物していた女子部員達は、キャアキャア嬌声を上げた。 「ねえ、見てよ!汚れたパンティの臭いを嗅いで勃起するなんて、最低!」 「よく、こんなので興奮出来るわね。本物の変態だわ!」 「本当にグロテスクね。こんなものを見せつけるなんて、恥知らずもいいとこよ!」 女子部員達に自分の股間を指差され、罵られた慎吾は恥辱で身震いし、目の奥が熱くなって涙が浮かんだ。彼は恥ずかしさのあまり、この世から消えてしまいたいと本気で願った。 「さてと、硬くなったから、オナニー出来るわね…さっさとしないと、そこをベルトで叩くよ!」 「ひっ、は、はい、ただいま…」 今日子に強い口調で促された慎吾は、慌てて硬くなったものを握り、懸命にしごき始めた。再度、女子部員達の嬌声が湧いた。 「キャア、皮が前後に動いてる!気持ち悪い!」 「男のオナニーって、本当に滑稽で醜悪だわ。最低よ!」 「よく女の前でオナニー出来るわね…やっぱり本物の変態よ!」 女子部員達の侮蔑が慎吾の胸を抉り、彼の精神を確実に蝕んでいった。それでも彼のものは、しごく度に硬度を増した。若い男子の悲しい性で、同級生の女子達から嬲られ、蔑まれ、度を超えた恥辱にまみれていても、硬く屹立してしまったものしごいて刺激を与える度に、快感が高まっていった。女子部員達の熱い視線が、自分の恥ずかしいものに集中しているのも、性的興奮に拍車を掛けた。 自分のものをしごく手の動きが知らず速くなり、限界まで硬く膨張して、全身の血液の大半が股間のものに集中したのではないかと思った時、それが破裂したように感じると同時に、呻き声を上げて夥しい白濁液を放出させた。 射精した瞬間、慎吾は自分の背骨も脊髄も神経も、今日子の手によって全て引き抜かれたかのように感じ、全身の力が抜けて、前のめりに倒れてしまった。この時点で、慎吾の気力は全て今日子に奪い取られ、以後彼女に反抗する事は永遠に不可能となってしまった。 今日子は、前のめりに倒れている慎吾の頭を蹴りつけ、顔に被せてあるパンティを剥ぎ取り、酷く命じた。 「勝手に寝ころんでるんじゃないよ!寝てる暇があったら、お前の液で汚した床を、舐めてきれいにおし!」 「は、はい…」 気力を全て奪い取られた慎吾は、よろよろと四つん這いになり、床に飛び散った自分の精液を舐め取り始めた。精液の生臭い味が口中に拡がり、床の埃のざらついた感触を舌に感じて、彼の惨めさを倍増させた。 「わあっ、汚い!よくこんなもの、舐められるわね!」 「犬でも、こんな汚いものは舐めないわよ。こいつは犬以下のケダモノだわ!」 「男って、ゴキブリみたいな真似が平気で出来るのね」 女子部員達の蔑みが、慎吾の頭の中で虚ろに反響し、彼は自分がとことんまで落ちぶれた事を思い知らされた。しかしこの時点では、慎吾は本当の奈落の底にまでは、まだ落ちていなかった。 床の精液を舐め終えた慎吾は、今日子から床に正座するよう命じられた。慎吾が正座すると、今日子は彼の髪を掴んで上に引っ張り、顔を上げさせると、 「口を大きく開くんだよ!」 と命令した。 慎吾がおずおずと口を開けると、今日子はカーッ、ペッと派手な音を立てて、彼の口に痰を吐き出した。痰のぬるりとした感触が口中に拡がり、慎吾は身震いして吐き気を催した。 「先公にチクった口へ、お仕置きしないとね…お前はあたしらの痰壺になるのさ。早く、飲むんだよ!」 今日子に命じられた慎吾は、吐き気を堪えて、彼女の痰を飲み込んだ。ぬるりとした痰の感触が食道で感じられ、慎吾は泣きたくなった。 「さあ、みんなもこいつを痰壺に使ってやって」 女子部員達は今日子に促され、カメラ係とビデオ係を交代しながら、喜んで慎吾の口に唾や痰を吐き出した。慎吾は吐き気で身震いしながらも、彼女達のぬるりとした唾や痰を飲み込んだ。 女子部員達が一通り、慎吾の口に唾や痰を吐き出すと、今日子は不意に慎吾の胸を蹴り、彼を仰向けに倒した。彼女は制服のスカートを捲り上げ、慎吾の顔に跨ると、そのまま腰を下ろした。先程パンティを脱いでいたので、陰部が丸見えだった。 今日子は慎吾の顔面手前で、一旦腰を止めた。目前に迫った今日子の濃い繁みに縁取られた陰唇は、慎吾を虐めて気分が昂ぶっていたのか、赤く充血してめくり上がり、ねっとりと濡れていた。本来なら、男に性的興奮をもたらす彼女の陰唇は、今の慎吾にとっては彼を焼き殺す火山の噴火口に見えた。 「チクった口を痰壺にするだけじゃ、お仕置きが全然足りないからね…人間便器にして、おしっこを飲ませてやるよ!」 今日子に残酷な宣言をされた慎吾は、今にも泣き出しそうな震え声で、必死に哀願した。 「そんな…止めて下さい。おしっこなんて、とても飲めません…お願いですから…」 「お黙り!痛い目に遭いたくなかったら、口をお開け!」 今日子に怒鳴られ、必死の哀願を一蹴された慎吾は、おずおずと口を開いた。彼が口を開けた途端、今日子の陰唇が微かに震え、黄色い奔流が噴き出した。勢いのある尿を口に注ぎ込まれた慎吾は、目を白黒させながら、喉を上下させて飲み下した。強いアンモニア臭と尿の刺激的な味が口中に充満し、喉を焼いて、胃に溜まっていった。 「うわぁーっ、本当におしっこを飲んでるわ!」 「信じられない!よく、おしっこなんか飲めるわよね」 「豚でも、おしっこなんか飲まないわよ。こいつは豚以下のうじ虫だわ。最低ね!」 撮影している女子部員達の蔑みが、慎吾の胸をズタズタに引き裂き、彼は自分が女の便器にまで落とされた事を実感して、目から涙が溢れ出た。 今日子は長い排尿を終えると、更に腰を落とし、尿で濡れた陰唇を慎吾の口に押し付けた。 「トイレットペーパーの代わりに、お前の舌を使ってやるわ。舐めてきれいにするんだよ!」 気力をすっかり喪失した慎吾は、涙を流しながら舌を伸ばし、今日子の陰唇をペチャペチャと音を立てて舐め始めた。 いい加減、慎吾に陰唇を舐めさせた今日子は、急に立ち上がり、周囲の女子部員達に声を掛けた。 「あんた達も、こいつの口におしっこしてみない?普通のトイレでするより、遥かに気持ちいいわよ」 女子部員達に否応のある訳がなく、歓声を上げてパンティを脱ぎ、次々に慎吾の顔に跨った。彼女達の尿で、慎吾の腹は膨れていった。中には尿の出なかった女子部員もいたが、それでも陰部はしっかりと舐めさせた。 全員が一巡したところで、今日子が全裸で床に横たわっている慎吾に言い放った。 「今日はこのくらいで勘弁してあげるけどね、もしもう一回チクったりしたら、お前の裸踊りやオナニーや、おしっこを飲んでいる写真とビデオを、学校中にばら撒いてやるからね!それと、明日からクラブ活動の時間になったら、体操服に着替えて、体育館のバレーコートに来るんだよ。お前をマネージャーという事にして、色々と雑用してもらうからね。分かったかい!」 部室の床に横たわったままの裸の慎吾は、今日子の酷い宣言を空虚な思いで聞き、目から涙が止まらなかった。 翌日の放課後、しばらく逡巡していたが、やっとの思いで体操服に着替えた慎吾は、重い足取りで体育館に向かい、バレーコートに近づいた。既に今日子と女子部員達は、練習を始めていた。 慎吾の姿に気がついた今日子は、ツカツカと彼に近づき、いきなりビンタを張った。 「ひいっ」 情けない悲鳴を漏らす慎吾に、今日子は凄い剣幕で怒鳴りつけた。 「何を今頃のこのこと来てるんだい!雑用係のくせに、あたしらより遅いとは、どういう事よ!」 「は、はい…申し訳ありません…」 慎吾はうなだれ、蚊の鳴くような声で詫びを述べた。体育館ではバスケット部やバトミントン部等他のクラブも練習しており、男子達も女子達も驚いたように今日子と慎吾に目を向けたが、今日子が周囲を見回すと、皆顔を背けて、自分達の練習に戻った。誰も今日子に関わりたがらなかった。 今日子が、女子バレー部の一年生と二年生に、慎吾を紹介した。 「みんな、こいつは竹中慎吾といって、私と同じクラスよ。一応三年生だけど、今日からマネージャーという雑用係にしたから、あんた達がやっていた雑用は、全部こいつにやらせて頂戴。一年生は、こいつに雑用のあれこれを教えてやって」 一、 二年生達はとまどい、互いに顔を見合わせた。すると、今日子が再度慎吾の頬を張った。 「ひいっ」 悲鳴を漏らした慎吾を、今日子は又も怒鳴りつけた。 「何ぼんやりつっ立っているんだい!みんなに土下座して、挨拶するんだよ!」 慎吾は慌てて、体育館の床で土下座し、下級生達に挨拶の口上を述べた。 「あの…僕は今日からバレー部のマネージャーになりました、竹中慎吾です…どうか、宜しくお願いします」 今日子は土下座している慎吾の頭を足で小突き、酷い命令を下した。 「ふんっ、それだけじゃ挨拶が足りないね…そのまま這って、みんなのシューズに挨拶のキスして回るんだよ!」 あまりの屈辱に慎吾の体は震えたが、今日子に逆らえる筈もなく、言われた通りに一・二年生達の足元に這い寄り、彼女達のバレーボールシューズの爪先にキスして、 「宜しくお願いします」 と言って廻った。 最初はとまどっていた一・二年生達だったが、中には明らかに侮蔑の表情を浮かべる女子も出て来た。慎吾が一通りシューズにキスして廻ったところで、今日子は皆に声を掛けた。 「さあ、みんな、練習再開よ…慎吾、お前はコートの後ろで球拾いでもしてな!」 練習中、慎吾はコートの外で走り回って球拾いをして、汗びっしょりになった。また、ボールを戻すのが遅いと、今日子の取り巻きである三年生部員達から、容赦なく平手打ちを喰らった。 時間が経過し、他のクラブが体育館から引き上げても、全国大会出場の常連だけあって、女子バレー部はまだ練習を続けた。 今日子は他のクラブが引き上げたのを見て、一旦練習を中断し、女子部員達と慎吾を呼び寄せた。 「みんな、こいつを台にして、スパイクの練習をするわよ…慎吾、お前はコート中央に立って、みんなのスパイクをちゃんとレシーブするのよ!」 球拾いでへとへとに疲れていた慎吾であったが、今日子に命じられ、急いでコート中央に立った。今日子は、一・二年生達に指示した。 「いい、こいつの体を的にして、順番にスパイクを打つのよ。これはコントロールの練習だからね…それと慎吾、きちんとレシーブ出来なかったら、罰に一枚ずつ服を脱いで、ストリップしてもらうよ。分かったね!」 今日子の宣言で慎吾は真っ青になったが、直ぐにスパイクの練習が始まった。まずは一年生からだったが、全員小学生からバレーで鍛えているだけあって、スパイクにはかなりの威力があり、運動はからっきしの慎吾は殆どレシーブ出来ず、ドッジボールのように体にボールを当てられるだけであった。 レシーブを失敗する度に、慎吾はジャージの上衣、下衣、体育館シューズ、靴下と次々に脱がされ、二年生の番が回ってきた時には、シャツとブリーフだけの惨めな姿になっていた。 一人目の二年生が打った強力なスパイクは、見事に慎吾の顔面にヒットして、彼は悲鳴を上げてコートに倒れた。 「慎吾、何グズグズしてるの!さっさと立って、シャツを脱ぐんだよ!」 今日子に厳しい口調で言われた慎吾は、べそをかきながら立ち上がり、シャツを脱いだ。いよいよブリーフ一枚だけになった慎吾に、一・二年生全員が喜んで手を叩き、 「あと一枚!あと一枚!」 とコールが掛かった。この時にはもう、一・二年生達は誰も慎吾を先輩と見なさず、自分達より格下の雑用係だと見下していた。 二人目の二年生が打ったスパイクも、慎吾のボディを直撃し、やはりレシーブ出来なかった。慎吾は最後の一枚となったブリーフを脱ぎ、皆の前で全裸を晒さなければならなかったのだが、一・二年生達の興味津々の視線が気になり、脱ぐ踏ん切りがつかなかった。しかし、そのためらいも今日子の一喝で吹き飛んでしまった。
今日子は、うずくまっている慎吾にツカツカと近づくと、彼の髪を掴んで引き上げ、顔を上に向かせた。 「口を開けるんだよ、うじ虫!」 ヒックヒックとしゃくり上げている慎吾が口を開けると、今日子はカーッ、ペッと、周りの一・二年生達に聞こえるように、わざと甲高い音を立てて、彼の口に唾を吐き出した。そして彼女は、後輩達に声を掛けた。 「みんな、こんな根性無しのうじ虫は、先輩でも男でもないからね。みんなもこいつを痰壺にしてやって」 今日一日で慎吾をすっかり軽蔑し切った一・二年生達は嬌声を上げ、大喜びで順々に彼の口へ唾や痰を吐き出した。下級生達の痰壺にされた慎吾の精神は、ボロボロに崩壊しつつあった。 「じゃあ、みんな、今日の練習は終了よ。早く帰りましょう…慎吾、お前は片付けと掃除を済ませてから帰るんだよ。いいね!」 慎吾に強く言い聞かせた今日子は、皆を引き連れてゾロゾロと体育館を出ていった。一人残された慎吾は、しばらく泣きじゃくっていたが、ノロノロと股間のものに結び付けられた細紐を解き、体操服を来て、ボールや他の用具を取りまとめて倉庫に直し、汗で濡れた床をモップで拭いた。モップ掛けをしながらも、涙が床に落ちるのを止められなかった。片付けと掃除を終えて体育館を出た時、周囲はすっかり暗くなっていた。 それからは、毎日が地獄だった。体育館で他のクラブが活動している時は、まだ平手打ちぐらいで手加減してくれるのだが、他のクラブが帰って女子バレー部だけになると、今日子は慎吾を裸にして、嬲りものにした。一・二年生達は慎吾を軽蔑し切っていた上、バレー部だけあって女子でも全員が、身長160㎝の慎吾より背が高く、彼は心身共に見下されていた。 同級の三年生は勿論、下級生の女子からも見下されて虐められる屈辱は、慎吾の精神を徐々に歪めていった。 ある日、今日子が黒光りする一本鞭を体育館に持って来た。 「親戚の知り合いに牧場を経営している人がいて、この鞭は親戚がその人から貰ったそうなんだけど、使い道が無いってこぼしていたから、あたしが譲り受けたの。あたしには使い道があるからね…ねえ、慎吾」 女子部員達は嬌声を上げ、慎吾は震え上がった。既に他のクラブは帰っており、体育館には女子バレー部だけで、慎吾は全裸にされている。もし無防備な裸に、あんな威力のありそうな鞭で打たれたら…慎吾は想像しただけで、全身に鳥肌が立った。今日子は、悪魔的な微笑を浮かべた。 「慎吾、そんなに心配しなくてもいいわ。今すぐお前に使おうとは、思ってないから…但し、ドジふんだりした時には、遠慮無く使うからね!」 慎吾は血の気が引いた。今日子は怯えている慎吾を横目に、部員達に声を掛けた。 「一年生と二年生は、レシーブの練習ね。慎吾は球拾いだよ」 バレーの練習が再会され、慎吾は全裸で走り回り、球拾いをした。最初の頃、一・二年生達はフリチンで走り回る慎吾を見て指差し、キャアキャア喜んでいたが、最近は当たり前の光景として、騒ぎもしなくなった。 走り回って球拾いするのは、結構ハードな運動量で、体力の劣っている慎吾は息が上がり、足がもつれ出して、ボールを返すのが遅くなってきた。不意に、今日子の一喝が飛んだ。 「慎吾!何をトロトロしてるんだい!お前、球拾いが嫌で、わざとゆっくりボールを返してるんだね!」 慎吾は息切れしながら、今日子に弁解した。 「ハアッ、ハアッ…そ、そんな、僕は真面目に、ハアッ、ハアッ、やっています…」 しかし、今日子は許さなかった。 「お黙り!言い訳なんか、聞きたくないよ!」 今日子は一本鞭を手にすると、頭上に振り上げ、全裸の慎吾に思い切り叩きつけた。空気を切り裂き、獰猛な唸りを上げて、黒光りする一本鞭が慎吾の裸身に絡みついた。 「ウギャアァーッ」 真っ赤に焼いたワイヤーで殴られた様な激痛と衝撃が、慎吾の骨まで響いた。今日子は再度鞭を振り、慎吾は鞭が襲ってくるのが分かってはいたが、あまりの激痛に筋肉が引きつって硬直してしまい、避けるどころか、体を動かすことすら出来なかった。 「グエェーッ」 一本鞭の第二撃を受けた慎吾は、獣じみた絶叫を上げ、そのまま床に倒れてしまった。彼の裸身に、赤い二本の筋が鮮やかに浮かび上がった。今日子は満足そうに笑った。 「アハハッ、さすがは牛追い用に使われるだけあって、人間相手だと効果抜群だね。お仕置きに丁度いいわ」 慎吾は床でピクピクと体を痙攣させながら、今日子の勝手な言い草を聞き、無念の涙を流した。 「わあっ、凄い威力ね。私にも使わせてよ」 「先輩、私も使っていいですか?」 同輩と後輩から鞭の使用をねだられた今日子は、苦笑いして答えた。 「うーん、使わせてあげたいけど、やり過ぎてショック死してもらっても困るからね…中世ヨーロッパの鞭打ち刑は、刑罰としては凄く軽い方だったんだけど、それでもショック死した者が後を絶たなかったらしいのよ…今日は試しに使ってみたけど、これからは慎吾がドジをふんだ時に、あたしの監督の下で使わせてあげるわ」 今日子は急に慎吾の方を向き、彼が横たわっている傍の床を鞭で叩いた。 「いつまで偉そうに、横になっているのさ!とっとと正座しな!」 「ひっ、ひいっ、ただいま…」 今日子に怒鳴られた慎吾は、鞭音に怯え、引きつる体を無理に動かし、何とか正座した。今日子は、無気味な猫撫で声を出した。 「慎吾、お前はあたし達の痰壺に使われてるけど、それだけじゃ物足りないわよねえ…前に便器になって、あたしら三年生のおしっこは飲んだけど、一年と二年のおしっこは、まだ飲んでなかったわね。どう、今日は飲んでみる?」 正座した慎吾は、顔が真っ青になった。直ぐに一・二年生から驚きの声が上がった。 「ええっ、慎吾先輩って、唾だけじゃなく、おしっこも飲むんですか?」 「信じられない、おしっこを飲むなんて…もう、人間じゃないですよね」 「うわっ、汚らわしい!想像しただけで、吐きそう!」 一・二年生の驚愕の声を聞いた慎吾は、真っ青だった顔が、度を超えた恥辱で逆に真っ赤になり、体を震わせた。今日子は、一・二年生の反応を見て面白そうに笑い、笑顔で慎吾に再び訊ねた。 「慎吾、一年と二年のおしっこを飲むの?飲まないの?はっきり答えてよ」 「…飲めません。とても飲めません」 慎吾は恐怖で身震いしながらも、なけなしの勇気を振り絞って、拒絶した。今日子が怒るかと思ったが、彼女は猫撫で声を続けた。 「あら、そうなの…お前に二つの道を選ばせてあげる。一つは、一年と二年のおしっこを飲む事。もう一つは、おしっこを飲まないで、鞭を我慢する事…どっちにする?」 慎吾は血の気が引き、恥ずかしさで真っ赤だった顔が、また真っ青になった。彼が答えられないで俯いていると、今日子は正座している慎吾の傍の床を鞭で叩き、怒鳴りつけた。 「人が訊ねているのに、無視するのかい!それなら、体中を鞭で打ってから、無理やり皆のおしっこを飲ませてやるわよ!」 鞭音が響き、震え上がった慎吾は、両手を前で振って哀願した。 「待って、待って下さい。お願いですから、鞭だけは許して下さい」 「だったら、どうするの!?おしっこを飲むのかい?」 今日子の問いに、慎吾は苦しげに顔を歪めた。 「いえ、おしっこは…ちょっと…」 今日子は、柳眉を逆立てた。 「まどろっこしいわね!お前が決められないなら、あたしが決めてやるよ。お前を男にするチャンスを上げるわ。おしっこを飲むのを断って、男らしく鞭打ちに耐える姿を、皆に見せてやりな!」 今日子が一本鞭を振り上げるのを見た慎吾は、慌てて懇願した。 「待って、止めて!鞭だけは止めて下さい…飲みます、おしっこを飲みますから、鞭だけは勘弁して下さい」 今日子は振り上げた鞭を下ろし、女子部員達の方を向いた。 「ねえ、みんな、聞いた?こいつは鞭を我慢するより、皆のおしっこを飲みたいんだってさ。本当に腑抜けだよ」 一・二年生の女子部員達はどっと笑い、口々に慎吾を嘲った。 「慎吾先輩って、最低ですね!男なら後輩のおしっこを飲むより、鞭を我慢しますよ」 「本当は慎吾先輩は変態で、女のおしっこを飲みたいんじゃないですか?だから鞭にかこつけて、おしっこを飲むって言うんでしょう」 「慎吾先輩、今ならまだ間に合いますよ。おしっこより鞭にしてと、キャプテンに頼んだらどうですか?」 下級生の女子部員達に嘲笑され、口惜しさと恥ずかしさで、真っ青になった慎吾の顔が又も赤くなった。はらわたが煮えくり返る思いだったが、慎吾は身震いして涙をこぼすしか出来なかった。一本鞭の激痛を思えば、下級生のおしっこを飲まされる方が、遥かにマシだった。 今日子は鞭を同輩に預けると、正座してうなだれている慎吾に近づいた。
「さすが優美ちゃん、積極性があるわね。さあ、遠慮無く慎吾を便器に使って」 優美は正座している慎吾に近づくと、 「慎吾先輩、さっきみたいに顔を上げて、口を開けて下さい」 と一応は丁寧語を使って、酷い事を言った。 彼女も今日子と同じように、ユニフォームの下衣とショーツを同時に膝まで下ろし、陰部を慎吾の口に押し当てた。しかし、皆の視線を意識してか、なかなか排尿出来なかった。このまま諦めてくれればと、慎吾は淡い期待をした。グズグズしている優美に、今日子が問い掛けた。 「どうしたの、優美ちゃん?おしっこしないの?」 「…すみません、先輩。催しているんですけど、なかなか出ないんです」 今日子は笑みを浮かべて、泣き出しそうな声で答えた優美の背後に廻った。 「優美ちゃんは、緊張し過ぎよ。バレーボールと同じで、肩の力を抜かないと、体が滑らかに動かないわよ。力を抜いて…ほら」 と今日子が優しく言い、後ろから優美の肩をポンと叩いた。その瞬間、優美の口から「あっ」と声が洩れ、陰部から尿が噴き出した。 慎吾は目を白黒させながら、こぼさないように優美の尿を飲んだ。今日子のと負けず劣らずアンモニア臭の強い濃い尿が、彼の喉を焼いた。優美も排尿を終えると、慎吾の舌で後始末させた。優美は慎吾に陰部を舐めさせながら、今日子に話し掛けた。 「先輩、男の人におしっこを飲ませるのって、凄く気持ちいいですね。私、病みつきになって、もう普通のトイレじゃ、おしっこ出来ないかも…」 「ウフフッ、あたしも同じよ。優美ちゃんに喜んでもらえて、よかったわ…さてと、他に慎吾を使いたい人はいる?」 今日子が一・二年生達に問い掛けると、今度は全員が手を挙げた。 結局その日は、これ以上の量は飲めないだろうと判断した今日子が、ジャンケンで二名だけ選ばせて、慎吾を便器に使った。女子部員達が帰り、一人全裸で残された慎吾は、体育館のトイレに駆け込み、泣きながらゲーゲーと胃の内容物を吐いた。吐いた際、改めて女子部員の尿の味と臭いが鼻につき、惨めさが更に涙を誘った。 下級生達に今日子の尿を飲まされるのを見られた上、その下級生自ら尿を飲まされて、自分に対する侮蔑の念がより一層強まったのを肌で感じ、慎吾の精神はどん底まで落とされた。しかし、この時の慎吾は、どん底にはまだ下があるのを知らなかった。 次の日から、女子バレーボール部員達の慎吾に対する虐めに拍車が掛かった。体育館で他のクラブが活動中でもビンタは当然で、慎吾を痰壺扱いするようになり、休憩時には順番で慎吾の顔を尻に敷いて、クッション代わりにした。球拾いで汗だくとなり、喉の渇きを訴える慎吾に、ペットボトルの水を自分の口でゆすいでから、彼の口に吐き出したりした。 他のクラブの部員達は、慎吾に対する陰惨な虐めを見て、眉をひそめたが、今日子と関わりになるのを恐れ、誰も何も言わなかった。 他のクラブが引き上げ、女子バレーボール部だけになると、慎吾はまず全裸にされた。今日子は一・二年生を喜ばすため、皆の前で慎吾にオナニーを強要し、歓声を上げさせた。慎吾の精神はズタズタに引き裂かれ、彼はもう下級生の前でも、顔をまともに上げられなくなった。 女子部員達は、もはや体育館のトイレは使わず、もっぱら慎吾の口を便器に使った。今日子は日によって鞭を使う部員を決め、慎吾が嫌そうな顔をしたり、もたついたりしただけで、鞭を振るわせた。一本鞭の威力は凄まじく、また基礎体力のあるバレーボール部員が振るうので、三発も打てば、慎吾は全身を痙攣させて、床にのびた。慎吾にとって、鞭は絶対の恐怖となり、女子部員が鞭を持って立っているだけで、身が竦んでしまった。また、どんなに嫌で恥ずかしい事でも、女子部員が鞭をほのめかすと、慎吾は慌てて言いなりになった。慎吾は身も心も、今日子だけではなく、女子バレーボール部員全員の奴隷に成り果てていた。この生き地獄は、慎吾が高校を卒業する日まで続いた。 慎吾が通っていた公立高校は、底辺高校と呼ばれるくらいに偏差値が低かったので、生徒の三分の一は就職し、三分の一は進路が決まらずフリーターになり、残り三分の一はFランクの大学や専門学校に進学した。今日子は、実業団バレー部からスカウトされていた。慎吾は三年生の一年間、酷い虐めのためにまともに勉強出来ず、成績はだだ下がりだった。しかし、一年生と二年生の時に勉強していた余力のおかげで、実家から遠くのFランクの文系私立大学にかろうじて入学出来た。慎吾がその大学を選んだのは、学力のせいもあるが、実家近くの公立高校から出来るだけ遠ざかりたいためだった。 大学生になった慎吾は心機一転し、高校三年生の時に出来なかった勉強を一からやり直した。遊び呆けたり、バイトに勤しむ学生が殆どのFランク大学で、高校の勉強をし直す慎吾は、周囲から奇異な目で見られて、浮いた存在になったが、全く気にしなかった。彼は酷い虐めを受けた地獄の高校生活を思えば、どんな事でも耐えられた。大学での勉学にも励み、教員免許も取得した。大学卒業時は就職氷河期で、同級生達は辛苦していたが、慎吾は幸いにも親戚のツテで、高校教師の職を得る事が出来た。 そして21年間、英語と現代国語の教師を続け、今年四月に母校である公立高校に赴任する事になったのだった。 慎吾は、教頭から三年生のクラス担任と女子バレーボール部の顧問を任された。 (来たくもなかった高校で、よりによって女子バレー部の顧問か…全く何の因縁なんだか…) 慎吾は内心うんざりしながらも、担任のクラスに向かった。彼は教壇に立つと、三年生になったばかりの生徒達によく響く声で挨拶した。 「皆さん、お早う。私がこの度クラス担任になった竹中です。このクラスには進学する人も就職する人もいますが、高校生活最後の一年間を充実して過ごして下さい。それでは、出席を取ります」 慎吾は出席を取りながら、筒井綾香という女生徒が気になった。彼女は綺麗な顔立ちだが、大柄で出席の返事にどこかふてぶてしい雰囲気が感じられた。彼はふと、思い出したくもない坂上今日子を連想した。 出席を取り終わった慎吾は、微かに頭を振って嫌な記憶を消し、現代国語の授業を始めた。しかし、底辺高校だけあって、黒板と教科書に目を向けているのは半分もおらず、他はスマホを弄っていた。 (携帯も無かった自分の頃は、隣りとのおしゃべりだったが、時代も変わったな…まあ、授業の妨害にならない限り、放っておこう) 慎吾は見て見ぬ振りで授業を進めるつもりだったが、筒井綾香の態度はさすがに見過ごせなかった。彼女は完全に背を向けて、後ろの女生徒と大声でペチャクチャとお喋りしていたのだ。慎吾は教科書で教壇をバシッと叩いて、彼女に注意した。 「筒井君、今は授業中だぞ!お喋りは休み時間にしたまえ」 綾香は前を向き、不服そうに口を尖らせた。 「でも先生、他校との練習試合の打ち合わせをしてたんですよ」 「だからそういう話は、休み時間にしなさい…筒井君は余裕があるようだね。だったら、黒板のカッコ内に当てはまる熟語を書いてみたまえ」 綾香はしぶしぶ黒板の前に行き、チョークを手にしばらく考えていたが、結局でたらめな漢字を書き込んだ。慎吾はわざとらしく大きなため息をつき、 「筒井君、これは中学生でも解る問題だよ。君は高校三年生なんだろう」 綾香は立つと、思ったより背が高かった。身長170㎝以上はあり、160㎝の慎吾を見下す格好となった。しかし、慎吾は背筋を真っ直ぐに伸ばし、綾香の目を見据えて、落ち着いた話し方をした。こうすれば背が低くても、生徒に教師の威厳を示せるのを、長い教師生活の経験から学んでいた。 「もういいから、席に戻って、教科書をきちんと読みなさい」 クラスメートの前で恥をかかされた綾香は、顔を真っ赤にして席に戻り、授業を続ける慎吾を面白くも無さそうに睨んだ。 授業が終わってクラブ活動が始まり、慎吾は体育館に足を向けた。スポーツがまるで駄目な慎吾は、バレーボールのルールさえも知らなかったが、顧問を命じられた以上、部員達に顔だけは見せておく必要があった。体育館に近づくと、嫌な記憶が次々に蘇った。 (もう二度と足を踏み入れるものかと思っていたのに…教師になって来るとは、本当に皮肉だ) 慎吾は内心うんざりしながら、体育館に入った。バレーコートの位置は昔と変わらず、女子部員達が汗を流していた。嫌だったが、バレーコートに近づき、キャプテンを尋ねた。すると、筒井綾香が前に出た。 「あら、竹中先生。私が女子バレー部のキャプテンですよ」 「ああ、筒井君がキャプテンだったのか…教頭先生から女子バレー部の顧問を命じられたので、部員達に挨拶しておこうと思ってね」
ある日、授業を終えた慎吾が職員室に戻ろうとすると、綾香が声を掛けてきた。 「竹中先生は、一応女子バレー部の顧問ですよね。一週間後に他校との練習試合があるので、引率の打ち合わせをしたいんですが…」 慎吾は一瞬嫌な表情を浮かべたが、断る訳にもいかなかった。 「…わかった。後で部室に行こう」 慎吾は職員室での片づけを済ませ、女子バレー部の部室に向かった。彼が部室に入ると、綾香と5人の三年生部員が待ち構えていた。ただならぬ雰囲気を何となく感じた慎吾は、25年前今日子に虐められた悪夢を思い出した。しかし、慎吾は教師の威厳を保つため、内心の動揺を押し隠し、意識して落ち着いた声を出した。 「練習試合の引率の話だったね…筒井君、日程はどうなっているのかな?」 しかし、綾香はそれには答えず、ニヤニヤと笑いながら、数枚の写真を慎吾の目の前に突き出した。 「先生、それよりこの写真を見てもらいたいんだけど…」 写真を見た慎吾は、驚きで目を見張り、心臓が口から飛び出しそうになった。それは高校時代の慎吾が、裸踊り・オナニー・飲尿等をしている恥ずかしい写真で、今日子の取り巻きが撮影したものだった。 「ど、どうしてこんな写真を…」 慎吾は震え声を出し、その写真を手に取ろうとしたが、綾香はさっと引っ込めた。 「私のママの旧姓は坂上で、名前は今日子よ…竹中先生は、坂上今日子という名前に覚えがない?」 綾香の問い掛けに、慎吾は頭を棍棒で殴られた様なショックを受けた。綾香は、坂上今日子の娘だったのだ。道理で背が高く大柄で、顔立ちやタイプが似ている筈だ。顔面蒼白で体を震わせている慎吾に、綾香は底意地の悪そうな笑みを浮かべて、説明した。 「ママにね、クラス担任のウザい先生がいるって、竹中先生の事を色々話したら、ママの高校の同級生だと分かってね。それでママが高校時代の竹中先生の事を詳しく教えてくれて、仕舞っていた写真とビデオを見せてくれたの…竹中先生は、信じられないような恥ずかしい事をしてたのね。写真とビデオ動画は、スマホに撮ったから、皆に一斉送信しようかな…この写真とDVDに焼き直したビデオ動画を教育委員会に送ってもいいし…」 「や、止めてくれ…」 慎吾は、震え声で懇願した。そんな事をされたら、学校にいられなくなり、教師の職を辞さなければならない。 「そうね…竹中先生が男らしく、私から力ずくで写真を奪い取られたら、止めてあげてもいいわよ」 綾香はからかうように、慎吾の前で写真をヒラヒラと振りながら、嘲るように挑発した。 「クソッ、よこせ!」 冷静さを失った慎吾は、後先考えずに綾香に飛び掛かった。しかし、身長160㎝の痩せた貧相な体で、スポーツに縁の無い非力な慎吾が、彼より背が高く大柄で、バレーで鍛えた屈強な女子高生達6人相手に、勝てる訳が無かった。慎吾はあっと言う間に取り押さえられ、よってたかって殴る蹴るの暴行を受けて、叩きのめされた。そして衣服を全て剥ぎ取られて、全裸にされた。 「竹中先生、そこに正座して!」 慎吾は泣きべそをかきながら、全身に受けた打撲で軋む体を何とか動かし、部室の床に正座した。綾香と女子部員達に弱味を握られた上、腕力で敵わないのを体に教えられた慎吾は、もう綾香に逆らう事は出来なかった。 「男は女の前で無理やりオナニーさせると、すっかり従順になるって、ママに聞いたから試してみるわ…竹中先生、オナニーして見せてよ。しなかったら、どうなるか…分かってるわね!」 「は、はい…」 綾香に強い口調で促された慎吾は、泣き顔で股間のものをしごき始めた。しかし、慎吾のものは萎びたままだった。 「まどろっこしいわね…こういう時は、顔に汚れたパンティを被せればいいって、ママが言ってたわ」 綾香は、制服のスカートを捲ってパンティを脱ぐと、汚れたクロッチ部分が鼻と口に当たるよう調節しながら、慎吾の顔にパンティを被せた。女子高生のきつい臭いを嗅がされ、彼のものは不覚にも硬く屹立してしまった。 「わあっ、あっと言う間に硬くなったわ。ママの言った通りね…竹中先生、これでオナニーで来るでしょう。早く、して見せてよ!」 綾香は可笑しそうに言い、他の女子部員達はキャアキャアはしゃぎながら、慎吾のオナニーをスマホで動画撮影している。 (同じだ…あの悪夢の高校三年生の時と、全く同じだ…) 慎吾は硬く屹立したものをしごきながら、高校三年生の時に受けた酷い虐めの記憶が次々蘇った。彼のオナニーを興味深げに見物しながらも、口汚く罵る女子部員達の口調も、高校三年生の時と殆ど同じだった。あまりの惨めさと恥辱に、慎吾の目から涙が止まらなかった。 間もなく慎吾は絶頂に達し、呻き声を漏らしながら射精した。25年前、今日子にオナニーを強制された時と同じく、全身の神経繊維を綾香に抜き取られたように感じ、気力を全て喪失して、がっくりとうなだれた。 しかし、綾香は慎吾に落ち込ませる暇を与える程、優しくはなかった。彼女は慎吾の顔からパンティを剥ぎ取ると、彼の顔を靴裏で押すように蹴り、床へ仰向けに倒した。綾香は横たわった慎吾の顔に跨ると、制服のスカートを捲り上げ、彼の顔にしゃがみ込んだ。綾香の充血してぬめった陰部が慎吾の顔に接近し、初めて今日子に尿を飲まされた情景と重なった。 「ママから、男を征服するには、おしっこを飲ませるようにとアドバイスを受けたの。女からおしっこを飲まされた男は、もうその女の前では顔が上げられないって、ママが教えてくれたわ…竹中先生、口を大きく開けて!」 抵抗する気力をとっくに失っている慎吾は、泣き出しそうに顔を歪めて、口をおずおずと開いた。その途端に、綾香の陰部から黄色い奔流が迸り、慎吾の口に注ぎ込まれた。彼は昔、今日子から尿をこぼさないように厳しく躾られた体験が蘇り、喉を上下させて、必死に飲み続けた。女子部員達はスマホで録画を続けながら、嬌声を上げた。 「キャーッ、本当におしっこを飲んでる!マジ、キモイ!」 「女生徒のおしっこを飲むなんて、教師どころか人間じゃないわよ。サイテー!」 「でも、ウザい教師を便器にして、おしっこを飲ませるなんて、チョーウケない?」 アンモニア臭の強い尿が舌を刺し、喉を焼き、胃に溜まっていくのを感じながら、女子部員達の嘲りを聞いた慎吾は、綾香と今日子が完全にオーバーラップし、自分が悪夢の高校三年にタイムスリップしたような錯覚に陥った。 しかし、教師である自分が教え子の女生徒から便器にされる屈辱と、思い出したくもなかった地獄の高校時代に引き戻された慎吾は、ショックのあまり思考回路が狂ってしまい、何とも的外れな事を考えていた。 (昔はわざわざカメラやビデオを用意してたが、今はスマホ一つで全ての用が足せるんだな…) 綾香は排尿を終えると、慎吾に追い打ちを掛けた。 「竹中先生の舌を、ウオッシュレットに使ってあげるわ。舐めて、きれいにして!」 (昔はトイレットペーパー代わりと言われたが、今はウオッシュレットか…) おかしくなった思考回路で、ずれた事を考えながらも、慎吾は舌を伸ばし、尿で濡れた綾香の陰部を舐め始めた。改めて舌に感じる尿の刺激的な味が大いなる屈辱を感じさせて、彼の思考回路を正常に戻し、あまりの惨めさに目から涙をこぼした。 懸命に舌を動かしている慎吾に、綾香は勝ち誇った声を掛けた。 「竹中先生は、もうこれで私の奴隷よ。もし私に逆らったら、今スマホで取った先生の恥ずかしい動画を、教育委員会と学校中に一斉送信するからね…でも、私だけが先生を虐めても面白くないから、下級生を含めて、女子バレー部全員の奴隷にするわよ。それと、明日からママが保護者兼OGとして、バレー部のコーチに来てくれるの。ママは竹中先生と会えるのを、凄く楽しみにしてたわ。ママが高校時代に使った鞭は、油紙に巻いて大切に保管しているから、今でも立派に使えるそうよ。ママには、バレーだけじゃなくて、鞭の使い方もコーチしてもらわなくちゃね。竹中先生も楽しみでしょう。アハハハ…」 綾香の陰部に付着した尿を舐め取りながら、彼女の高笑いを聞いた慎吾は、絶望で気が遠くなりそうだった。25年前の地獄の高校時代に戻って、また虐められる…それも母娘揃って…慎吾は舌を動かしながら、一体何の因縁なのかと、自分の運命を深く呪ったのだった。 終わり |