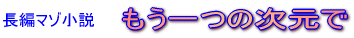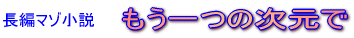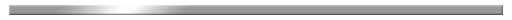
その2
「ふふ・・ちょうどいいわ。お前に私の部屋を見学させてやるわ。ありがたいと思いなさい!」
「はい、所長様、ありがとうございます」
「連れてきて」
傍らにいた調教女師に命じて所長の倉橋まり子様は部屋を出てちょうど真ん中に位置する大きな扉を開けて入っていった。
中は豪華な造りだが所々にその部屋に似つかわない鎖やフックなどがカベや天井などに埋め込まれたいる。
私は四つん這いでその部屋に入り入り口の横で土下座した。
その部屋の真ん中には両手首に着けられた手枷の鎖をフックに引っ掛けられて吊られている牡奴隷がいた。
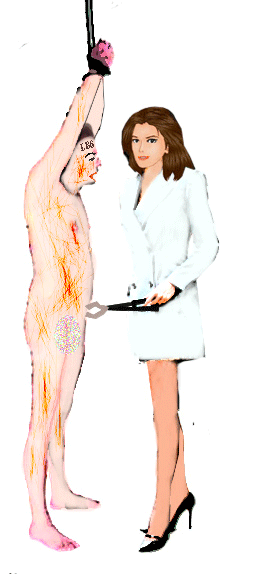 |
彼は爪先立ちになるほど吊られて小さな声を絞り上げるように言っている。
「申しわけ・・ございませんでした・・どうか・・どうかお許し下さいませ・・お願いでございます・・」
すると彼女はゴルフクラブのアイアンを手にとって彼の身体を殴りつけた・・・
「ぎゃう〜・・」
彼の叫び声が部屋中に響く・・・
「おい、新入りのお前、顔を上げていいからこっちにきてよく見てご覧!」
「はい、所長様・・」
私はあわてて前に進み、吊られている彼の斜め前に行き彼を下から見た・・
「あっ・・」
思わず声をあげて驚いてしまった。なぜなら彼の顔は原型が分らないほど腫れ上がり体には無数の傷痕・・・火傷ののように膨れた皮膚や紫色になった打撲の痕・・そして切られたような皮膚からは血が滲んでいる。
うう・・ひどい・・私は思わず目を背けてしまった。
「ほら、どうしたのよ。こいつを見ろっていてるのよ。命令が聞けないの!」
私は彼の酷い姿を目を赤くして見た・・
「こいつがなんでこんな目にあってるか分る?ふふ、こいつはこんな風にされて当たり前の事をしたのよ。今日、私の足置き台として使ってやっていたのに私がちょっとヒールを体に突き刺してやっただけなのにこいつは私のハイヒールに手を触れたのよ。この汚らわしい手で」
「も・・・申し訳・・ぎゃあ〜・・」
なんと彼女はペンチで彼の皮膚をつまみ上げそれを捻り上げている・・・
「ふふ・・ほらっ!」
「ぎゃあ〜・・・・」
あまりの残虐さに目を反らす私に・・
「よく見ろ!まぬけ」と叱責しながらさらになぶり続けるまり子所長様・・・
ただ、ヒールの痛みに耐えかねてつい手が出てしまっただけなのに・・・こんな目に合わされるなんて・・
自分の事のように体が震えてきた・・・
「くぼんだ顔からうつろな目でなおも許しを請う牡奴隷・・・彼の体にはLB68という奴隷番号が刻まれているのがやっとわかった。それほど彼の身体は痛めつけられて変色していたのである。
「ううっ・・・」
彼のすすり泣きに私もつられてしまいそうだった。 |
「新入り、こいつの事かわいそうだと思う?ふふ、そんなんじゃここで生きていけないよ。お前達は牡奴隷だって事を忘れるんじゃないわよ。ほら、こっちに来てご覧」
彼女の命令に即座に従い豪華な机の後に連れていかれた。
「ああっ?」
またも私の目に飛び込んできた光景・・・それは見たこともない椅子・・・・透明なアクリルのような筒の中に正座の状態で入れられて顔だけは真上に向かされているその顔の上にはその筒にピッタリのサイズの小さな穴がたくさん開いた弁のようなものが乗っているその上には豪華な椅子の座面部分が連結されている。
つまりその椅子に座ると全体重が彼の顔面に掛かる事になる。しかもそれだけではない彼が正座させられているのは江戸時代の拷問の石抱きに使ったようなギザギザの段になっている石の上だった。
そして体のいたるところに針のようなものが刺されており、その針にコードのようなものが付いていた。
「よく、見てることね。新入り奴隷!」
彼女は上着を脱いでその椅子に座るとちょうど注射器を押し下げるピストンのようにその透明な筒の中にあった弁が下に押し下げられた。その重みを彼の顔がまともに受ける事になる。見ていると彼の体は苦痛でピクピクと痙攣しているように見えた。さらに苦しいらしく何か叫んでいるいるようだったが外には全く聞こえないしくみになっていた。
さらに彼女は椅子に取り付けられたボタンを押しボリュームつまみのようなものに手をかけて言った。
「この虫けらの声でも聞かせてあげようか?」
そういってもうひとつのスイッチをオンにした。すると中から・・
「ひぃ〜ぐっぐ・・助けて〜お慈悲を・・・・」
と悲壮な声がスピーカーを通して聞こえた。そして彼女はマイクに向ってこう言った。「いいわ、お前にお慈悲をあげるわ。私は慈悲深いからもう少し苦しめてあげようねぇ、ふふ」
そしてつまみをクイッと右に回した。すると筒の中の牡奴隷のつんざくような叫び声が聞こえ、彼の体がさらに大きく痙攣した。皮膚に刺されている針からは火花のようなものが出たのだった。・・・・電気ショック・・・私はすぐにその装置を理解した。彼の絶叫を楽しげに聞いていた彼女は私にむかってこう言った。
「この椅子はねスレイブ・チェア(奴隷椅子)って言うんだけど、牡奴隷の間では地獄椅子って言われてるらしいの、ふふ・・楽しいでしょう。私は毎日この強制所の中からこの椅子の係りを選んで、こうして嬲ってやってるの。だからお前もいつかはここに入れてやるからね。ふふ・楽しみにしてらしゃい!あはは・・」
「そうそう、この椅子を考え出したのは小学校6年生の女の子らしいわよ。拷問機器メーカーが牡奴隷を嬲る装置をインターネットで募集したらみごとにこれが採用されたらしいの、そして考え出したのが12歳の女の子だったてわけ。その子は中学受験でむしゃくしゃして座ったままで牡奴隷を虐める方法をずっと考えてたらしいわ。素敵な子だと思わない?将来はここにスカウトしたいくらいね。あはは・・」 |
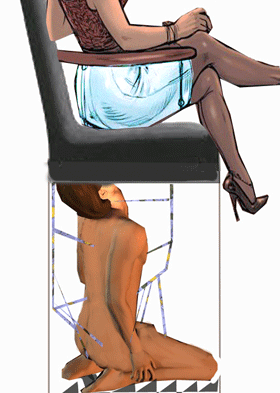 |
私はおそらく失神もできず苦しみ続けるこの牡奴隷に自分を映し出し、恐怖に顔を引きつらせていた。たぶん彼はなんの粗相もしていないのに彼女にこうして嬲られているんだと思うと、彼女への恐怖がさらに増してきたのだった。その場で這いつくばって頭を床に擦りつけ必死に許し請うしかなかった・・・
「お、お許し・・下さい・・・どうか・・・お許しを・・・・」
「こんな風に嬲られて、惨いとか思ってるんじゃない?ふふ・・だとしたら思い違いよ。お前達は人間じゃないのよ、姿形だけは私たちに似てるけど全然違う生物なのよ。虫けらとよく似てるわね、だから蚊を潰す時にかわいそうなんて思わないでしょう。それといっしょなのよ。お前達が苦しんでも誰もかわいそうだなんて思わないのよ。それが分るようにしてあげたのよ、あはは・・」
彼女の高笑いが部屋に響いた。
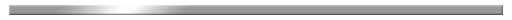 |